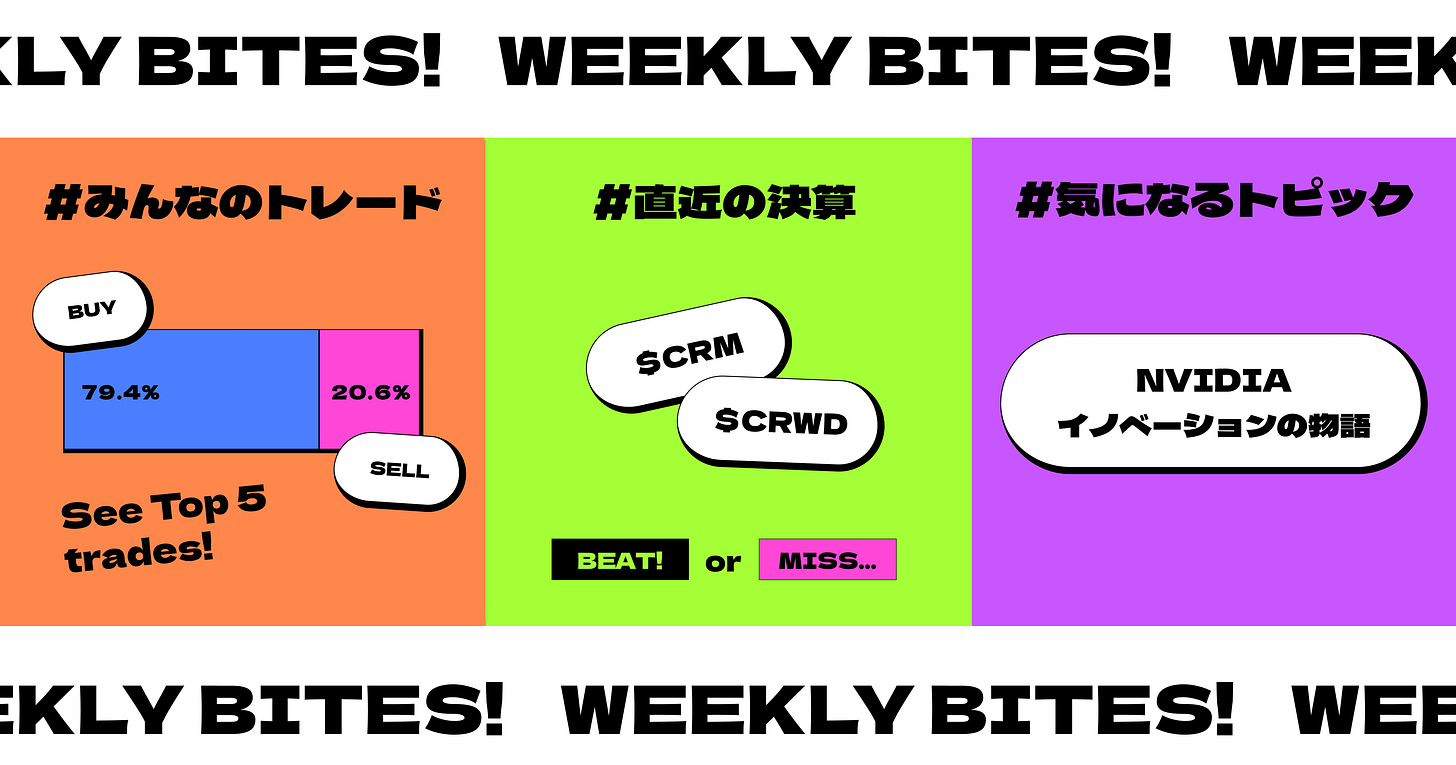Weekly Bites! 🍩 vol.17 | Nvidia、イノベーションの物語
2023年6月5日号
Weekly Bites Vol.17へようこそ!著者のブライアン・ユンです。今週の気になるトピックは、先週に引き続き、Nvidiaについてです!
目次
始める前に、念の為ですが、私たちの配信しているコンテンツは投資のアドバイスではなく、ここで述べることはすべて筆者(ブライアン・ユン)の個人的な意見と調査に基づいており、Woodstockの見解を代表するものでもありません。個人的にポジションを保有している可能性もあります。WeeklyBites!に掲載されている内容は、あくまで情報提供のみを目的としていますのでその点ご理解ください。
#Company Updates
#プレスリリース
クリックして読んでね👉 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000092154.html
本日プレスリリースを出させていただき、直近のいくつかの新機能についてのアナウンス、及び5月の取引総数+66%(前月比)など各種スコアで過去最高を更新したことを発表しました!いつもwoodstock.clubを応援してくださる皆様、本当にありがとうございます!これからもWoodstockの冒険を見守っていてください!🚀
#アプリ・アップデート
アプリの新バージョン1.1.23をリリースしました!
バブルチャートや新ポートフォリオカードをタイムライン及びソーシャルメディアなどにシェアできるようになりました。
取引の際に必要な ID/パスワードが補完できるようになりました。
マーケットオープン、クローズ時に市場動向などの通知が送付されるようになりました。
UI/UX の改善を行いました。
いくつかのバグを修正しました。
#今週の気になるトピック
#Nvidia、イノベーションの物語
前回のWeeklyBites!では、1993年に戻って、Nvidiaの創業ストーリーをご紹介し、ジェンセンとチームが、会社が非常に厳しい状況の中、どうやって生き残り、他の90社ものビデオチップメーカーとどのように差別化したのかについてお話ししました。私同様、このストーリーを楽しんでいただけたなら幸いです。
今日のWeeklyBites!は、Nvidiaのイノベーションの物語をご紹介したいと思います。先週は、ゲーム業界向けに作ったビデオチップについてお話ししましたが、その後、どうデータセンタービジネス(今やゲーム事業よりはるかに大きい: グラフ参照)を始め、それを成長させるために何やってきたのか、早速ご紹介しましょう!
本日の記事は、woodstock.clubのユーザーの方(ナスダッ子さん、ポールさん、お話を聞かせていただきありがとうございました!)からのお話と、2022年3月27日に公開されたポッドキャスト「Acquired」シーズン10 エピソード5をもとに、ご紹介します。
https://www.acquired.fm/episodes/nvidia-the-gpu-company-1993-2006
前回のエピソードの終盤で、1997年にRiva128チップが大成功し、会社を救ったストーリーをお話しました。また当時エヌヴィディアはTSMC(他社が設計した半導体を製造する、台湾の半導体ファウンドリー)と取引するには規模が十分でなかったため、第2層のファウンドリを使用したことについてもご紹介しました。その後、Riva128が大成功を収めると、ジェンセンはTSMCに接触し、1998年に戦略的パートナーシップを結ぶに至りました。
https://www.nvidia.com/content/timeline/time_98.html
2017年に行われたTSMCの30周年記念式典でも、この彼らの最初の出会いの話が共有されました。そのストーリーを少しご紹介しましょう。
"ジェンセン・フアン "と名乗る人物から手紙をもらい、ファウンドリー事業について私と話したいので電話してほしいと言われました。それでジェンセンに電話したら、電話口でジェンセンが “しーっ、静かにして!モリス・チャンから電話がかかって来たんだ! "と言っているのが聞こえ、それが私たちのビジネスの始まりでした。” (モリス・チャン)
"モリス、まず最初に、私があなたに手紙を書かなければならなかった理由は、あなたの営業所に何度も電話したけどうまく繋いでもらえなかったからです。営業担当のみなさんは今のお得意様にかかりきりで規模の小さい私たちのことを取り合ってくれなかったんです。" (ジェンセン・フアン)
https://www.tsmc.com/static/archive/video/30th%20Anniversary%20Forum%20Transcript_all.pdf
そんな始まりを経て、今はTSMCとパートナーであるNvidiaは、1999年にブランド名を変更したチップ「Geometry Force」の第1世代を生産し(GeForce)、第1世代カードGeForce256を発売しました。今日まで、Nvidiaはすべてのグラフィックチップに「GeForce」ブランドを使用しています。
2017年に米国株への投資を始めたナスダっ子さんは、実際にこのモデルを当時お持ちだったそうなのですが、何年も後にまさのこのNvidiaの株に熱狂することになるとは、当時は知る由もありませんでした。これこそまさに「運命の出会い」ですね!
https://twitter.com/AvFRoosevelt/status/1661718952370925574?s=20
このGeForce256は、トランスフォーム、ライティング、トライアングルセットアップ/クリッピング、レンダリングエンジンを1つのプロセッサーで提供する、初の完全統合型グラフィックプロセッサユニットとして、「GPU」という言葉を一般化したことでも有名になりました。
ではこの時、IntelとAMDは何をしていたのでしょう? IntelもAMDもCPUとマザーボードを製造しています。グラフィックチップのメーカーは90社もあり、誰しもが最高品質のグラフィックを提供しようと争っていたことは、ご説明したとおりです。サウンドカードやTVチューナーのカードはどうでしょう。IntelとAMDの立場からすれば、このような競争の激しい、利益率の低いビジネスに手を出す理由はありませんでした。結局、各カテゴリー(サウンドカードやビデオなど)の勝者であっても、IntelやAMDのPCIカードをマザーボードに組み込むことになる。彼らにとっては、黙って競争させる方がずっと楽だし、もしこの市場が十分に大きくなれば、ビデオやサウンドのチップを自分達でも製造して、直接マザーボードに組み込むことになるだろうと考えていました(実際そうしたのです!)どちらにしてもそんなカードを買うのは、本当にハイエンド製品が欲しいマニアだけだと。
ジェンセンはこのことをよく分かっていました。自分たちのチップをプロセッサユニットである「GPU」と呼ぶことで、「CPU」メーカー(Intel、AMD)に対して、「Nvidiaは違う立ち位置にいて、コモディティ化することはない」というメッセージにもなっていました。
*CPUとはCentral Processing Unit」の略称で、中央演算処理装置。一方でGPUとはGraphics Processing Unitの略称で、画像処理装置。画像処理や動画処理関係の演算は膨大な計算量となるため、高い処理能力が求められCPUだけでは処理が追いつかないので、画像処理に特化したデバイスであるGPUを使用する必要があります。
1999年、NvidiaはIPOを果たし、その後数年間、MicrosoftのXBoxのグラフィックスを担当するなど、大型の契約を獲得しその収益は順調に伸びていきました。この間、Nvidiaはプログラマブル・シェーダーとライティングを備えたGeForce 3を発表しました。これは、ゲーム開発者がゲーム内でシェーダー(陰影の処理)とライティングを動的にプログラムできるようになったことを意味します。これは、ハードコーディングされたグラフィックからプログラマブルなグラフィックになったということで、大きなイノベーションとなりました。この時点で、Nvidiaは、ゲーム開発者がストーリーを語ることを可能にするプログラマブルGPUを作るという夢を達成したのです。
しかしながら、2003年以降、Nvidiaの売上は頭打ちとなります。マイクロソフトとの取引のような大きな契約は、マイクロソフトがNvidiaからマージンを搾り取るように、低いマージンで行われたため、Nvidiaとしての粗利率はあまり良くありませんでした。そんな中、ATI(90社あった競合他社の中でNvidia以外で生き残った唯一の会社)もプログラマブルグラフィックスを開発していました。そして、市場が統合されゲーム産業が発展し続ける中、IntelとAMDがじっとしているわけもなく、Intelは本格的なGPUの開発を発表、そしてAMDはATIを買収して、Nvidiaにとって強力なライバルが現れる形になったというわけです。そんなわけで、IPOから数年後、Nvidiaの状況はあまりよくありませんでした。
時を同じくしてこの頃、Nvidiaは思いがけないチャンスに遭遇し、それが数年後にもっと大きなものへとつながっていくことになります。スタンフォード大学の量子化学の研究者がジェンセンを呼び出し、言うには、自分の計算モデルをNvidia GPUにロードして実験したところ、スタンフォード大学のスーパーコンピュータ(CPU)を使って数週間かけて計算していたのが、NvidiaのGPU上で実行するとわずか数時間で計算が完了したというのです。研究者はこの技術によって、どれほど効率よく仕事ができるようになったことかと、ジェンセンに感謝を伝えたのでした。
彼の話を聞いて、ジェンセンは「ハッ!」としたのでした。Nvidiaは科学的コンピューティングに大きく賭ける一方で、競合他社はゲーム用の優れたグラフィックスを作ることに集中していたのです。woodstock.clubのユーザーで、Capital Groupで半導体業界を担当した元リサーチアナリストのポール・リーは、Nvidiaにとってこの重要な時期に起こったエピソードを話してくれました。
"数年前、NvidiaがIntelの統合グラフィックスへの参入に脅かされていた、そのころにJensenに会ったとき、彼はGPUの並列処理能力の素晴らしさを話し続けていたのを今でも覚えています。しかしながら、その素晴らしい能力を活用するための著名なアプリケーションが当時ほとんどありませんでした。幸運なことに、急拡大中のAIアプリケーションは、このNvidiaの同時に計算を処理する能力から多大な恩恵を受け、そして、その結果、GPUとNVidiaは今日の(ほぼ)1兆ドル企業になったのです。”
"並列計算 "というのは、GPUの固有の機能でありメリットです。CPUはクロックスピードは高いが、計算命令を一つずつ処理するのに対し、GPUは計算命令をパラレルで同時処理するので、映像や画像処理に有利になるのです。”
https://hpc.llnl.gov/documentation/tutorials/introduction-parallel-computing-tutorial##Whatis
画像や映像の処理において並列処理の利点は元々明らかでしたが、ポール氏が指摘するように、この能力を活用する著名なアプリケーションは、この時点ではほとんどありませんでした。株価が低迷し、収益が頭打ちになり、競争が激化してゲーム用グラフィックスの市場シェアが奪われる中、Nvidiaは取り乱して研究開発に多額の資金を費やし、コンピューティング用GPU周辺のインフラとソフトウェアを構築しているように見えたことでしょう。しかし、この時のこの努力のおかげで、AI企業は自分たちのニーズをこのGPUで満たすことができる様になったのです。
数年後、世のAIのアプリケーションは、このGPUこそ、同時計算ができるという点でAIモデルの機械学習に最適であると気づくことになります。このことはまさにNvidiaがその基礎を築いたと言っても過言ではないと言うことです。グラフィック・チップというのは、画像や映像処理という性質上、行列やベクトルの計算を行います。AIモデルのニューラルネットワークに必要な計算は、偶然にもこれと非常に似ていたのです。ポール氏は、この点でジェンセンは非常にラッキーだったと言っていました。もちろん、どんなビジネスをするにも、運はつきものです。しかし、確実に言えることは、ジェンセンとNvidiaはイノベーションを起こし続け、生き残るために戦い続け、夢に次ぐ夢を実現させたということです。
エヌビディアの物語を興味深く見ていただけたでしょうか。今日のエピソードでは、Nvidiaがどのように革新を続け、ジェンセンがGPUの予想されるユースケースにつまずきながらも、GPUコンピューティングの基礎を築き、AI産業という大きなチャンスを掴むことができたのかについてお話させていただきました。本日の気になるトピックは、ここまでとさせていただきます!NVDAの第2回をお読みいただき、本当にありがとうございました。
#みんなのトレード
Woodstock.clubアプリ上で、先週(5/29-6/4)売買された銘柄ランキングはこれだ!
#直近の決算
ここではwoodstock.clubで取り上げたいくつかの決算のまとめについて改めて、ご紹介しておきます。(BEAT!は、決算が予想よりもよかった時、MISS...は予想より悪かった時、INLINEは予想通りだった時をそれぞれ意味しています。)
CRM 0.00%↑ Beat/Beat
https://twitter.com/woodstockclub/status/1664024034026356736
CRWD 0.00%↑ Beat/Beat
https://twitter.com/woodstockclub/status/1664027247869857792
今日は以上です!今日のコンテンツが参考になった方がいらっしゃいましたら、ぜひ「いいね!」と「購読」をお願いします!そして周りの皆さんにもシェアしていただけると嬉しいです。
Weekly Bites! vol.17 is brought you by…
【免責事項】
・米国株式等の金融商品の取引に際しては、契約締結前交付書面等をよくお読みください。
・米国株式等の売買等にあたっては、株式相場や金利水準、為替水準等の変動や株式等の発行者等の業務や財産の状況等の変化による価格等の変動によって損失が生じるおそれがあります。
・投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の判断でお願いいたします。